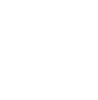2022.2.18
▼はじめに
このコラムは、「SDGsについて関心があるけど、イマイチ全体像がわからない。」「SDGsっていったい何ができるんだろう」「SDGsってビジネスにどうやって活かすんだろう」という、当たり前の疑問を抱えて、モヤモヤしているみなさまのためのものです。
不定期に小さな記事を少しずつリリースしています。
なぜなら、私自身がお客さんから「SDGsって何からやればいいの?」って聞かれて困ったことが過去にあるからです。ぜひコツコツ一緒に学んでいきましょう。
最近は、多くの事業者がSDGsを事業再構築補助金を活用した新規事業開発のヒントにしています。まずは、知ることから始めましょう。
▼大阪府堺市は、SDGs未来都市宣言をしています。
私たちが、活動拠点としている大阪府堺市は、SDGs未来都市としてその取り組みを中期計画(2021~2023)で発表しています。その計画書冒頭の将来像のところでは、以下の様に宣言されています。
〇堺は、古くから世界と交流し多様な文化や価値観などを受け入れ、「もののはじまりなんでも堺」と謳われるほど、様々な新しいものを生み出してきた都市。
堺市 SDGs未来都市計画 (2021~2023)
〇この伝統を受け継ぎ、市内企業の高い技術力などの強みを生かしながら、イノベーションを創出し、未来への貢献をめざす。
〇また、先進的な環境政策の推進により経済と調和を図ることとあわせて、多様性を認め合う、誰一人取り残さない社会を築くことで持続可能な未来を創造する。
そんな熱い堺市のWEBサイトですが、ときどき面白いものも紹介してくれています。それが、今日の本題は、「えつ?!こんなことでもええのSDGs」です。
これは、“国連広報センター”が発表している「持続可能な社会のためにナマケモノにもできるアクション・ガイド」というパンフレットです。私たちの大好きなユーモアがあふれる、楽しい資料ですので、ここで紹介させてください。
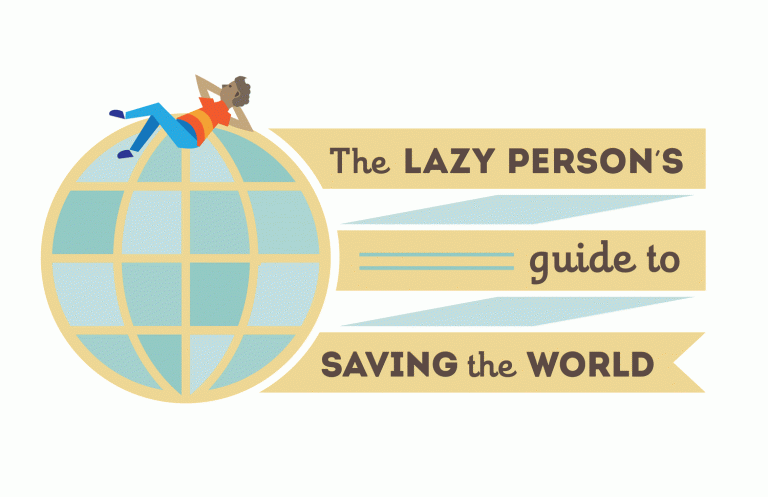
▼ナマケモノにもできるアクションってなんだろう?!
それにしても、ナマケモノにもできるアクションっていったいなんでしょうね?
このガイドによるとこの世界を持続可能な社会にするためのアクションは、レベル1からレベル4までの4段階に分かれています。
まず一番簡単なレベル1では、“ソファに寝たままできること”が紹介されています。少し笑っちゃいますね。
内容は、「電気機器はこまめに電源を切ろう」や「振り込みは、窓口ではなくモバイルでしよう」「SNSでSDGs関連のニュースを見つけたら“いいね”だけではなくシェアしよう」など。他にも人権問題への意思表示や情報発信などが提案されています。確かにソファでゴロゴロしててもできることばかりです。
続くレベル2では、“家にいてもできること”。新型コロナの影響で行動規制の中でも取り組めることがありそうです。
具体的には、「シャワーは短時間、髪の毛は自然乾燥」「肉や魚は控えめにして、残り物は早めに冷凍保存しよう」や「エアコンの設定は冬は低め、夏は高めに設定しよう」などなど。家の中でできることが他にもたくさん。ほとんどが省エネ関連ですね。
そして、レベル3では、“家の外でできること”です。
買い物関連では、マイバッグの利用や、地元のお店で買うこと、訳あり品やサステナブル・シーフードを選んだり。「行きつけのお店がサステナブル・シーフードを活用しているかも確認しよう!」となっています。
恥ずかしながら私、この“サステナブル・シーフード”という言葉を初めて知りました。
私と同様に初耳の方向けに・・・
サステナブルシーフードとは、“環境に配慮した漁業を営む漁業者によって獲られた魚介類のこと”を言うのだそうです。環境と生物に配慮している漁業者が漁獲した魚(天然魚)には『MSC認証』、養殖場で獲れた魚(養殖魚)に『ASC認証』を認証機関が、付与しています。ゴール14の「海の豊かさを守ろう」に深く関係しています。水産庁が『平成28年度 我が国周辺水域の資源評価』にて、漁獲可能量制度の対象魚種のうち50魚種84系群が枯渇していると公表。水産物をたくさん消費する我が国ですが、実は安く魚介類を購入できたり、お店で食べられたりするのが不思議なほど海洋環境と生物が危機的状況に陥っているのが現状です。
このような事態が起きた背景には、違法漁業・過剰漁業といった漁業者に関する問題、そして規格外や不人気のために漁獲されても廃棄されてしまう食品ロス問題、海洋環境の汚染があります。
SDGs Media noteより
確かに、年に何回かは、産地偽装や漁獲高の激減なんてニュースを目にしますよね。
▼ナマケモにもできるSDGs最高レベルはどんな内容か?
レベル4は、“職場でできること”として、「差別などの人権問題や女性や若者の支援」「省エネやCO2の削減」「廃棄物の削減とリサイクルの推進」などが提案されています。
大企業では、すごく先進的な取り組みがされていることも増えてきたようですが、私たちの周りの小規模事業者では、まだまだ始まったばかり。もしかしたら、自宅での取り組みの方が進んでいたりするかもしれませんね。
▼SDGsは生活の隅々にまで関係がある
このガイドブックの最後には、「このガイドでは、あなたができることのほんの一部しか紹介できていない。あなたが一番関心を持てる目標やさらに積極的にアクションを起こすための方法についてもっと情報を収集をしてくださいね。」と締めくくられています。
確かに、17のゴールと169のターゲットは、私たちが朝起きてから夜寝るまでのすべての事柄において“世界を変えるきっかけ”があることを示しています。
私も、まずは、このパンフレットのレベル1について自分の休日から何ができるか?考えてみたいと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
中小企業診断士 山本 哲也
少しでも興味があれば、一度お会いして(ZOOM対応)お話をしましょう。(無料です。)
私たち堺なかもず経営支援センターは、さかいSDGs推進プラットフォームに参画しています。