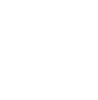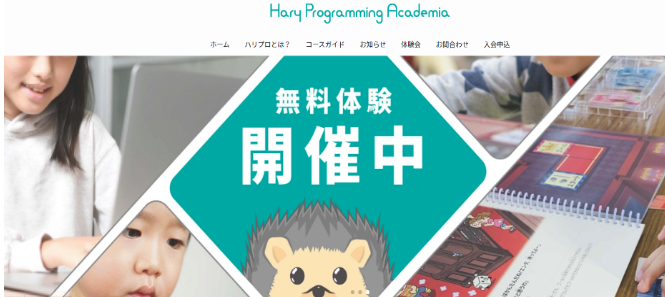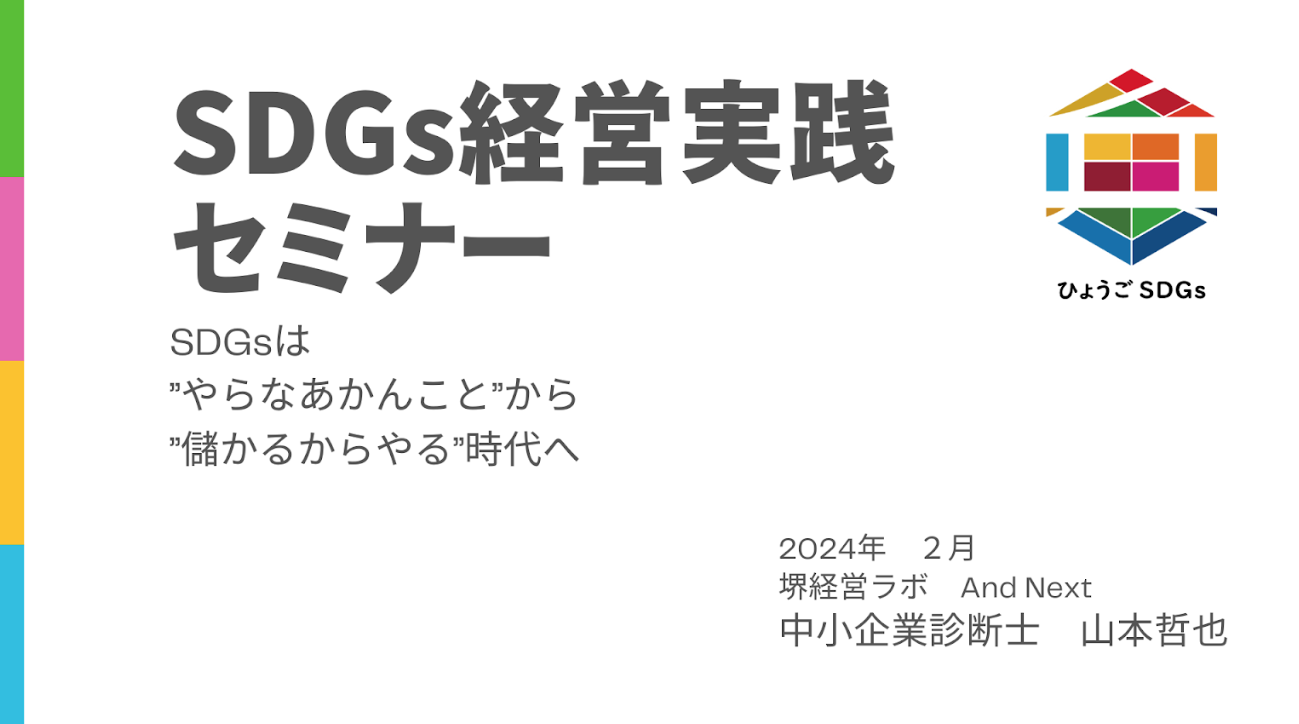本日、ご紹介する“ひと”は、ハリープログラミングアカデミア代表の小谷祥子さんです。また、彼女は、株式会社 Team ifの代表取締役でもあります。
ハリープログラミングアカデミアとは?
今回ご紹介するハリープログラミングアカデミア(以下「ハリプロ」)は、大阪市東住吉区で2022年4月に開校したばかりの子ども向けプログラミング教室です。
大阪市東住吉区は、日本で最ものっぽビルである、あべのハルカスの南東に位置し、杭全(くまた)や住道矢田(すんじやた)など難読地名があることから分かる通り、歴史ある閑静な住宅街です。一方で、駒川中野商店街という大阪有数の商店街や東部市場という市場などもあるため、とても大阪らしい風景の街並みの地区でもあります。
有名な施設としては、セレッソ大阪の本拠地や世界陸上の会場として世界的にも有名な長居競技場などもあり、子育てにぴったりの町とも言えそうです。
プロジェクト参画のきっかけ
今回、ご一緒させていただいたきっかけは、株式会社Team ifによる「新規事業参画メンバー大募集!」の情報を、WEB上でたまたま見つけて応募したことにあります。
つまり、その新規事業プロジェクトが、“ハリプロ”プロジェクトです。このプロジェクトは、「東住吉区に新しいコンセプトのプログラミング教室を、独自開発のカリキュラムでスタートさせる」という内容でした。
Team ifでは、これまでも他社との協業で大阪市中央区にて子ども向けプログラミング教室の運営をしていましたが、今回は、Team ifの地元でもある東住吉区に直営教室を新規開設しようとの考えからスタートしました。
街のあちこちにプロクラミング教室が…
ところで最近、プログラミング教室を見かけることが増えていると思いませんか?私の暮らす大阪堺市でも、新規オープンの広告が増えているように感じます。
実は、プログラミング教室の新規開設は、ちょっとしたブームとなっていて、全国展開の大手教室もあるほどの盛り上がりを見せています。
その理由は、2020年度(令和2年度)から小学校においてプログラミング教育が必修化されたためだと思われます。
さらに、中学校や高等学校においても必修化は、進んでいますし、2025年1月の大学入試共通テストの科目に入ることもすでに発表されています。
「情報」という名称の科目となり、内容は、プログラミングやデータサイエンスに必要な統計処理、情報リテラシーの知識などを学ぶ科目になるそうです。これにより「情報」は「国語」や「数学」などと並ぶ基礎教科ということになります。
文部科学省が公開している関係資料を見ると
①技術革新の急速な発展
②人口減少と高齢化
③新たな社会(society5.0)の到来
などが予見される中で、「未来に向けてポジティブな姿勢でよりよい社会と幸福な人生を創る力を子どもたちに育みたい」という想いがあるようです。
つまり、これからの社会がどのように変化するかが予測しずらい世の中になってきている。「今、小学校で教えていることが全く通用しない社会になるかもしれない?!」と考えた時に、我々大人が子どもたちにできる教育とは?
と考えた結果、この結論に至ったようです。
必ずしもプログラミングがあれば、やっていけると考えたわけではなく、未来の技術進歩、海外の動きなどを総括して考えると、情報教育は避けられないことだと考えているようです。
一方で、海外に目を向けてみると、一部の国では、必修科目にしているようですが、各国ともまさにこれからというような状況です。
ハリプロプロジェクトでも、地元東住吉の子どもたちにもこのような社会の変化に対応できる人材に育つ機会を提供したいと考え、新教室開設へと動きました。
ハリプロプロジェクトで小谷代表が目指していること
ハリプロは、プログラミング教室ではあるのですが、単に子どもたちにプログラミングスキルを学ぶだけではなく、プログラミング学習を通して“新しいことを生み出す力”や“社会で活躍するための基本的な能力”を学んでもらうことを目的にしたカリキュラムを提供しています。
特に、ハリプロがこだわっているのは、失敗を許容するマインドです。つまり失敗力です。
失敗力、失敗する力を大切に
失敗力?!失敗する力?! 我が子には、成功させてやりたいやん!?
まずは、いま、世界の舞台で活躍している人たちについて思い浮かべてください。
いかがでしょうか?私が思い浮かべた人たちは、新しい取り組みや事業にチャレンジして、一度は、「失敗した」人たちばかりです。中には、いまだにときどき失敗をして、残念がっている人たちも多くいらっしゃいます。
日本では、失敗したら恥ずかしいという文化があるためなのか、いつ頃からか子どもたちは、失敗を恐れて、自分たちの潜在的な能力を閉じ込めてしまっている気がします。
しかし、今や、チャレンジをする人間が評価され、リーダーシップを発揮する時代へと変わりつつありますし、国もそのような人材育成に舵を切りつつあります。
ハリプロでは、そんな一昔前の学校教育や親御さんの意識に疑問を感じ、一足先に新しい人材育成に取り組み始めました。
集合教育を受け始める前後の幼少期にトライアルアンドエラーを繰り返すことのできる環境を整えれば「チャレンジ力、やり抜く力が身につけられれる」
そんな教室を作れば、東住吉の子どもたちの将来に大きな影響を与えられると考えたのです。
ハリプロで身につく4つの力
失敗力
世の中に出れば、失敗から学ぶことの方が多くなります。それなのに、子どもの失敗を責めることは、彼らの成長を止めることに繋がります。チャレンジして、失敗して、またチャレンジすること(トライアルアンドエラー)これを繰返し、目標に向けてやり抜くこと。つまり、子どもたちに失敗から学ぶ機会を作りたいのです。失敗力が備われば、自然と問題解決能力も備わります。
論理的思考力
長い人生では、行き詰ったと感じるような大変な経験をすることがあります。そんなときには、要素を分解・整理し、シンプルにリフレーミングすることで、簡単に解決への道筋を見つけられることがたくさんあります。」
「ハリープログラミングアカデミアでは、事象だけでなく、自分の感情も併せて自ら記録します。それによって、次に繋げ、組み立て、考える力を養うことができるからです。これを楽しく続けられるような工夫を最大限にしています。
想像力/創造力
今後、AIが人間に代わって仕事をする時代になっても、社会から必要とされる人とは、想像力を駆使して新しく何かを創造できる人です。
プログラミング学習では、学んだコードを組み合わせて、自由な発想で、オリジナルの答えを見つけます。唯一無二の答えがないことを体感してもらいます。
コミュニケーション能力
将来、自分のアイデアを実現するためには、必ず誰かの協力が必要になります。自分のアイデアを他人に伝えることが出来なければ、誰かの共感や協力を得ることはできません。
これからより重要になるコミュニケーション能力を養うため、ハリプロでは、定期的な発表会を行い、プレゼンの機会を提供しています。そこで、学んでほしいことは、人に伝える勇気とそれを共有できたときの喜びです。さらには、他人の考えを理解し共感する力です。
新規事業プロジェクトもトライアルアンドエラー
このような壮大なプロジェクトですので、やはり、簡単には、進みませんでした。小学校前でのチラシ配布も新型コロナウイルスの流行とともに、学校から断られたり、真冬に企画した体験イベントでは、換気のおかげで外と同じような室温の教室で実施したり・・・。
体調不良で、当日キャンセルが出ることが多々ありました。
また、ミーティングは、オンライン・オフラインのハイブリッドを余儀なくされたり、課題が多く、深夜にまで及ぶことも多々ありました。
それでも、来場してくれた子どもたち全員が、夢中で取り組む様子を拝見してメンバーは、プロジェクトの成功を確信しました。


まとめ
コロナのこともあり、スロースタートではありましたが、プロジェクトは、無事テイクオフしました。
私が、今回のプロジェクトが成功できていると感じている理由は…
①イベントや教室に参加してくれた子どもたちが全員楽しそうに夢中になっている。
②それを見るご家族が素直に喜んでらっしゃる。
③単なる労働という訳ではなく、やりがいを感じて参画しているメンバーが集まった。
ビジネスとしては、まだまだできることがあり、成長への余白はたっぷりありますが、関係人口が徐々にでも増え、みんなが価値を感じるリアルビジネスなんて、なかなか簡単に出会えるものではありません。
今後も成長がとても楽しみなハリープログラミングアカデミアです。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事に興味をお持ちの方は、小谷社長におつなぎしますので、こちらからお問い合わせください。
お問合せ>>
特に
「お子さんを通わせてみたい」とお感じのご家族のみなさま
「PRのお手伝いをしたい。」「先生をしたい」とのスタッフ希望のみなさま
からのご連絡をお待ちしています。
今回ご紹介したハリープログラミングアカデミアのように、当社では、大阪や堺を中心に活躍する新規事業開発の支援をしていますので、お気軽にお問い合わせください。
どんなお役立ちができるかはお話を聞いた上でご提案いたします。まずは、面談(リアルまたはオンライン)、メール、電話で無料打ち合わせをお申込みください。当社が得意な範囲は、そのまま提案させていただきますし、不得手な分野には各種専門家やお仲間になれそうな地元事業者をご紹介します。
<本日のお客さまの紹介>
株式会社Team if ハリープログラミングアカデミア
住所:大阪市東住吉区桑津3丁目15番36号